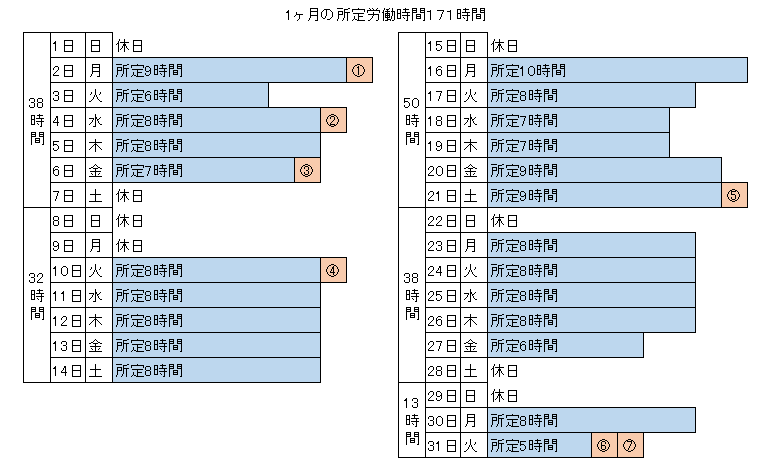難しい?!1ヶ月単位の変形労働時間制を徹底解説
1ヶ月単位の変形労働時間制を既に採用している会社、あるいは、これから採用したいと考えている会社は多いと思いますが、この1ヶ月単位の変形労働時制は、意外と難しく、導入する際には注意が必要です。
そこで、今回は、この1ヶ月単位の変形労働時間制について、制度の内容や導入のための要件等はもちろん、就業規則の記入例、どういった場合に時間外労働(残業)・休日労働に該当するか?なども含めて詳しく解説していきたいと思います。
この制度を理解することは、導入している又は導入を検討している会社にとっては重要ですし、そこで働く労働者の方々にとっても、例えば、残業代計算が適性になされているかどうかを確認する意味でも大変意味のあることだと思います。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは?
現在、法定労働時間は労働基準法で1日8時間、週40時間(一部の事業場は44時間)と定められています。つまり、会社が従業員の方を働かせる場合、所定労働時間は、この時間以下にする必要があります(もちろん、この時間を超えて働かせてもOKですが、その時間は時間外労働(残業)になります)。
しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すると、変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間以下になっていれば、特定の日、あるいは特定の週において、法定労働時間を超えて所定労働時間を設定できることになります。
例えば、ある週の労働時間が10時間×5日間、でも違う週は6時間×5日間と設定した場合、週平均は40時間となります。1日10時間は法定労働時間の8時間を超えていますが、違法にはなりませんし、残業代も発生しないことになります。
このように、1ヶ月以内の間で、忙しい時期と暇な時期があるような会社だと、この1ヶ月単位の変形労働時間制を採用することで、余計な時間外労働をさせる必要がなくなることになります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するための要件
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するためには、
書面による労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて、以下のことを定める必要があります。
①1ヶ月以内の一定期間を平均して週の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、各日、各週の労働時間を具体的に定めること
②労使協定による場合は、有効期間の定めをすること
③労使協定の場合は、所轄の労働基準監督署に届け出ること
が必要となります。
就業規則で定めるか、労使協定を使うか、どちらが良いのか?
1ヶ月単位の変奇労働時間制を採用するに当たり、その定めを就業規則に定めるか、労使協定により定めるかは、会社が決定しますが、この2つのうちどちらを選べばよいのでしょうか?
個人的には、就業規則のほうが良いと思います。なぜかというと、労使協定の場合は、有効期間の定めをしなければならないため、有効期間が切れる前に再度、労使協定を締結し、さらに、労働基準監督署に届出なければなりませんが、就業規則の場合は、一度、定めてしまえば、有効期間は無いので、そのまま継続して制度を利用し続けることができます。
変形期間は1ヶ月未満でも良いか?
1ヶ月単位の変形労働時間制は、「1ヶ月」と名前がついていますが、必ず変形期間を1箇月にしなければならないわけではありません。最長で1箇月ということになるので、4週間単位や2週間単位で採用しても構わないことになります。ただ、必ず、就業規則等で、その起算日を明記しておく必要があります(例えば、変形期間を1ヶ月とするならば「毎月1日を起算日とする」という形で明記します)。
ただ、採用している多くの会社が1ヶ月(暦日数)で変形期間を設けていると思います。
変形期間が1ヶ月の場合の、労働時間の総枠は?
1ヶ月単位の変形労働時間制は、変形期間を平均して1週間の所定労働時間が法定労働時間を超えないように設計する必要があります。実際に設計した制度が、以下の時間を下回っている必要があります。
変形期間を1ヶ月とした場合で
31日の月の総枠=177.1時間
30日の月の総枠=171.4時間
29日の月の総枠=165.7時間
28日の月の総枠=160時間
各日、各週の労働時間の特定
1ヶ月単位の変形労働時間制は、あらかじめ各日の労働時間を明確にしておく必要があります。会社が、任意に最初に決めた労働時間を会社の都合で変更するようなものは認められませんので注意が必要です。
よく就業規則に「1ヶ月を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で1日8時間、週40時間を超えて労働させることがある」とだけ書いて、具体的な各日、各週の労働時間を定めていない場合がありますが、これは認められないことになります。
そもそも就業規則には、必ず、始業時刻と終業時刻を明記しなければならないので、各日の労働時間の長さだけでなく、始業終業時刻も定めておく必要があります。
なお、毎月、シフト表や勤務割表を作って運用しているところもあると思いますが、その場合でも、始業終業時刻の定めは必要です。複数のパターンがある場合は、すべて記載し、そのパターンの組み合わせの考え方、シフト表の作成手順、周知方法等をあわせて定める必要があります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合、残業時間はどうカウントしたらよいか?
変形労働時間制を採用しない場合で1日8時間・週40時間が所定労働時間の会社の時間外労働(残業時間)の計算は、単純に1日であれば8時間を超えた時間、週であれば40時間を超えた時間をカウントすればよいだけなので簡単ですが、変形労働時間制を採用した場合は、これが若干複雑になります。
まず、1日ごとでみていきます。
1日の所定労働時間を8時間以内に設定した日に残業した場合は、8時間を超えた部分の時間が割増賃金が必要な時間外労働になります。下記の図で言うと、②と④がこれにあたります。
もともと8時間を超える時間を所定労働時間として設定している日については、その設定した時間を超えた部分が割増賃金が必要な時間外労働になります。下記の図で言うと①と⑤がこれにあたります。
1日ごとで時間外労働を確認したら、次は週ごとで確認します。
下記の図の③を見てください。6日の所定労働時間は7時間なので1時間残業しても、1日ごとでみたら法定労働時間の8時間以内なので、割増賃金は必要ありません。週の所定は38時間でなので、2時間までは法内残業ということになります。
週ごとで確認したら、次は月で確認します。
すでに、1日ごとと週ごとでみた時間外労働となった時間を除き、変形期間の総枠の限度時間を超えた部分が割増賃金の必要な時間外労働になります。以下の図では、31日に月なので、この月の月間法定労働時間の限度は、先に書いたように、177.1時間です。
下記の図では、もともとの所定労働時間が171時間ですから、177.1時間までは6.1時間あります。
下記の図の①~⑤まではすでに時間外労働としてカウントしていますので、月で見た場合は、まだ6.1時間残業させても割増賃金は付かないことになります。
よって、下記の⑥及び⑦は、1日で見ても8時間未満なので割増賃金が必要な時間外労働になりません。週でみても同様ですので、⑥およ⑦は割増賃金の必要の無い残業ということになります。
こういった形で時間外労働をカウントする際には、順番にかつ慎重にカウントしていかなければならないので注意してください。
1ヶ月単位の変形労働時間制の就業規則規程例
(変形労働時間制)
第○条 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制によるものとし、始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のいずれかとする。各人ごとの具体的な各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに書面により通知する。
| 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | |
| A勤務 | 7:00 | 15:00 | 12:00~13:00 |
| B勤務 | 8:00 | 16:00 | 12:00~13:00 |
| C勤務 | 9:00 | 17:00 | 12:00~13:00 |
2 休日は、1ヶ月に6日を交替で与えるものとし、月曜日を起算日とする1週間に1日を確保する。各人ごとの具体的な休日は、勤務割表により起算日の7日前までに書面により通知する。
まとめ
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している会社は、結構多いのですが、厳密に運用しようと思うと、かなりの制約があることがおわかり頂けると思います。私は、仕事柄、多くの会社の労働時間制度を見てきましたが、変形労働時間制を採用している会社のうち、少なくない数の会社が、知らないうちに運用方法間違えているケースも少なくありません。
法令違反にならないよう、しっかりとした知識と運用方法が求められます。